元公務員の私が「妻を代表」にして法人を設立して良かった7つの理由
— 副業禁止の回避と家族のための資産づくりを両立する実践録 —
本記事は、妻を代表に据えた法人スキームで副業禁止の回避をしながら、家族のためにキャッシュフローを最大化してきた7年分の学びをまとめたものです。事業は 不動産賃貸業 太陽光発電事業 WEBマーケティング 物販業 の4本柱。具体的な数字・図解・装飾で“読める”構成にしています。
プロフィールと前提
以降は「できた/できなかった」を具体例と数字で示します。各論では装飾・枠・図で要点を一瞬で把握できるようにしました。
① 法人の経費を使って 生活費を圧縮 できた
法人を通すと、課税前に支出を落とせます。結果として手残りが増え、家計の体感は「節約していないのに貯まる」。
- 家賃・水道光熱費の事業按分
- スマホ・Wi‑Fiなどの通信費
- PC・プリンタなどの備品、サブスク
※按分率は業務実態に沿って根拠づけ。領収書・議事録・業務記録を残すと監査耐性が高まります。
② 「法人の肩書き」で 経営者と話ができる ようになった
元公務員としては縁遠かった領域でも、法人格+役職があると金融機関・士業・不動産・再エネ事業者と話が早い。情報の質が変わり、意思決定のスピードも上がりました。
- 不動産:管理会社・仲介会社との仕入れ打合せがスムーズ
- 太陽光:O&M(保守)・売電契約の相談が前提共有で楽
- WEB:広告代理店・制作会社との取組で単価交渉が通る
③ 自覚ができ、お金の使い方が変わった
「これは投資か?浪費か?」の基準で支出を判断。意思決定の質が上がり、ムダが目に見えて減りました。家計もビジネスも利益体質へ。
④ 家賃の一部・通信・備品などを合法的に経費化
自宅兼事務所の按分
- ワークスペース比率で家賃の20%を「地代家賃」へ
- 電気・水道・ガスも業務使用率で按分
根拠:間取り図/面積比/稼働時間など。按分計算メモを都度保存。
通信・サブスク
- スマホ・Wi‑Fi:業務利用分を計上
- 有料クラウド・SaaS:WEBマーケ運用に紐づけ
⑤ 自家用車は 法人リース にして 全額損金
業務利用を前提に、車両を法人リースへ切替。リース料・保険・車検・メンテがまるごと経費になり、キャッシュフローが安定しました。
| 項目 | 個人利用 | 法人リース |
|---|---|---|
| 月額支出 | ¥50,000(手取りから) | ¥50,000(損金処理) |
| 税務処理 | 対象外 | 経費化で課税所得↓ |
| 維持費 | 別途負担 | リース料に包括 |
📊 図解:年間の 節税効果 シミュレーション
前提:売上 800万円/経費 35%/役員報酬含む/法人実効税率 23% 想定。個人事業(超過累進)との単純比較モデル。
※単位は万円・概算。実際は役員報酬・社会保険・青色控除等で最適解が変動します。
⑥ 補助金 がもらえた(対象の広がり)
法人化により、小規模事業者持続化や設備導入系の補助金にアプローチ可能に。WEBマーケ経費・機器の導入・広告出稿に実際活用できました。
⑦ 旅行も/家族の食事も 要件次第で一部経費
不動産視察や太陽光サイト確認に合わせて移動・宿泊を計上。家族同席の食事も、議題・参加者・目的の記録と領収書の宛名で業務関連性を担保。
- 旅費:行程・訪問先・打合せメモを保存
- 接待交際:議事、目的、参加者、金額、支払手段の記録
よくある質問(FAQ)
Q. 副業禁止に触れませんか?
A. 代表=妻/私は役員という設計で、就業規則上の兼業禁止と利害相反を回避しています。加えて、以下を徹底。
- 兼業許可が必要な職種は、在籍先の規程を確認(収入の有無・時間基準など)
- 私の名義での契約・請求・公の登記はしない(実務は補助に限定)
- 会社設備・勤務時間を使わない、守秘義務と競業避止を厳守
Q. 家族の食事や旅行は、どこまで経費にできますか?
A. 業務関連性と証憑が鍵です。以下を満たすと認められやすくなります。
- 食事=接待交際費:目的・議題・参加者・支払者・金額をメモし、領収書の宛名は法人名
- 旅行=出張旅費:行程表・訪問先(物件/発電所/取引先)・写真・打合せ記録を保存
- 家族同伴分は原則私費。業務参加者の分のみを経費に
Q. 車を全額損金にする条件は?プライベート利用がある場合は?
A. 法人名義のリース+業務使用が前提です。
- 車両は法人契約。保険(対人・対物)も法人名義
- 業務日誌(日付/行先/距離/目的)をつける
- 私用利用がある場合は走行距離等で按分し、役員貸与分は
「給与課税/金銭精算」のいずれかで処理
Q. 家賃の按分はどう決めればいい?
A. 面積比×稼働時間など合理的基準で算定します。
- 例:ワークスペース6㎡/居住面積30㎡=20%
- 在宅勤務日の実稼働率を掛け合わせて最終按分率を決定
- 根拠資料:間取り図・写真・稼働記録。メモを毎期保存
Q. 補助金はどうやって取る?どれを狙う?
A. 事業計画と経費の整合がポイント。狙い目は小規模事業者持続化(販促)や、設備・IT導入系。
- 流れ:公募要領チェック → 事業計画(課題/解決/KPI/資金計画)→ 見積取得 → 申請
- 採択後に発注・支払・実績報告。事前発注は対象外に注意
- 実績物(広告、LP、設備)は成果物の証跡を保存
Q. 役員報酬と社会保険はどう設計しましたか?
A. 定期同額原則に従い期首で設定。期中の変更は原則不可なので、キャッシュフローと節税のバランスを事前に試算。
- 役員報酬:法人税と所得税・社保の総額が最小になるゾーンを試算
- 社保:代表(妻)を原則加入。私の加入要否は報酬・就業実態で判断
Q. 妻を代表にする場合のデメリットや注意点は?
A. 法的責任と与信が代表に集中します。家庭内で役割と権限を明文化しましょう。
- 代表印・銀行権限の管理ルール、社内規程を整備
- 与信審査は代表の属性影響大。個人資産の担保には慎重に
- 将来の承継・相続・離婚等のリスクも合意書で予防
Q. 会計と証憑管理のコツは?
A. クラウド会計+クラウドストレージで即時保存が鉄則。
- レシートはスマホでスキャンし、日付_用途_金額で命名
- 議事録・見積・契約・成果物をフォルダ分け
- 月次で科目レビュー。按分・旅費・交際費は注記を残す
まとめ:法人化はテクニックではなく 家族の防衛戦略
法人を活用すれば、副業禁止の回避と家族のための資産づくりを両立できます。まずは現状の支出を“事業視点”に並べ替えることから始めましょう。
※本記事は体験に基づく一般的情報です。具体的な税務・法務判断は専門家へご相談ください。


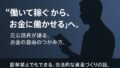
コメント